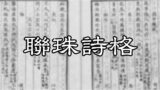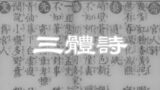スポンサーリンク
『三體詩(三体詩)』全作品テキストデータ
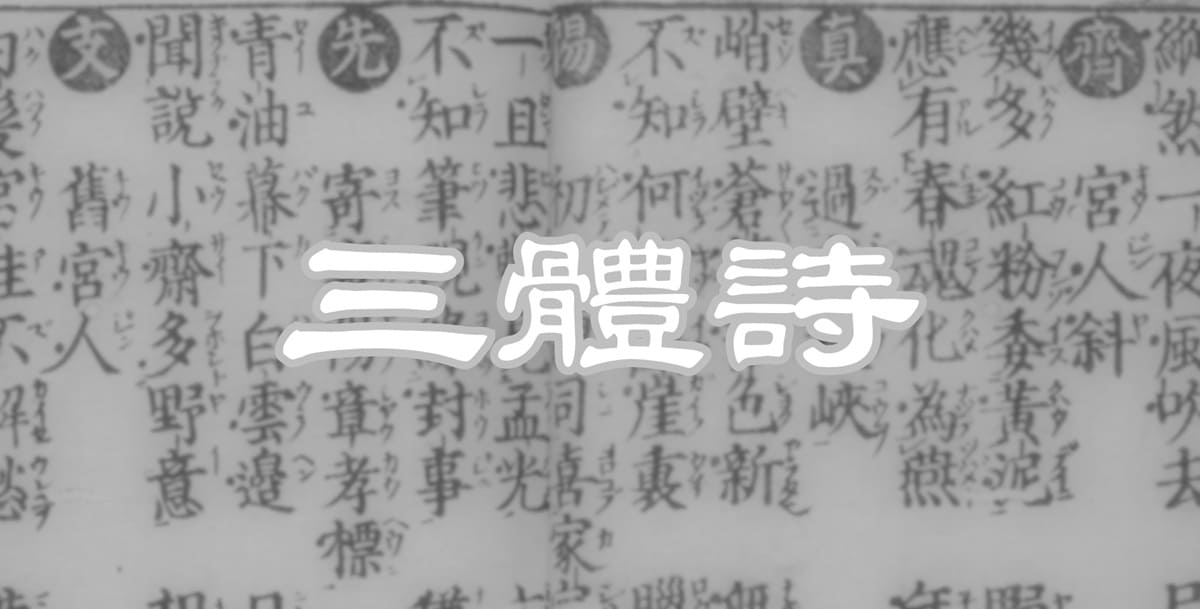
底本
『國譯三體詩』(『國譯漢文大成』 文学部 第6巻)
宋・周弼 編
日本・釈 淸潭 譯・講
大正10年(1921年)3月 國民文庫刊行會 刊行
データ作成の基本方針
このサイトには、『三體詩(三体詩)』の作品をテキストデータとして収載している。内容は上記の底本に従うことを基本とするが、明らかに誤っている点、欠けている点等は他本を参考にして改め、補い、その旨を注記する。また、後述のとおり、一定のルールに基づいて底本の字を改めた部分もある。
白文については出来得る限り正字を用いることとするが、文字コードの制限等によりそれがかなわない場合は、略字等も用いることもある。しかし、複数の異体字のうちどれが正字であるか見解の分かれるものもあり、「正字(と私が見なす字体)による白文」のみでは、字体の違いが原因で検索にヒットしない事態が頻発する可能性が高く、データベースとしての操作性が損なわれることが否定できない。そこで検索の便宜をはかるため、正字による白文の下に常用漢字(新字体)による白文を( )で括って表示することとする。
読み下し文については底本の訓読を参考にしながらも、構文や意味をより理解しやすい訓読になるよう手を加えたが、あくまで私が最も適切と考える一例を示したにすぎず、他の訓読法も当然あり得るし、私の読みが明らかに誤っている場合もあるかと思われる。ご指摘、ご批正等あればコメントいただければ幸いである。なお、読み下し文の漢字は常用漢字を基本とし、仮名は歴史的仮名遣いを用いる。
なお、底本では、草木の花の意味の場合も「花」字を用いず「華」字を用いている。確かに起源としては「花」字は「華」字の俗字として作られたものであるから、「華」字を正字、「花」字をその俗字と見なして、正字と見なす「華」字に統一するのも理のないことではない。しかし一般的には「花」と「華」を異体字の関係とは見なさず、別々の字として扱うのが普通であり、私自身もそう考える。よって、底本で「華」と表記していても、他本等を参考に通常「花」と表記すべきだと考えられるところは当テキストデータでは「花」に改めている。
また、底本では「閑」字を用いず、すべて「閒(間)」字に統一している。「ひま」「しずか」の意味においては「閑」「閒(間)」の両字は通用するから、このこと自体に問題はない。ただデータベースとして利用する観点からは「閑」と「閒(間)」を使い分けたほうが便利であると考える。よって、底本で「閒」と表記していても、「ひま」「しづか」の意味のところは、当テキストデータでは「閑」に改めている。
データの利用方法
あらためて説明することでもないが、[Ctrl]+F で検索ボックスを表示させて目的の語句を検索することができる。ただ、「『聯珠詩格』全作品テキストデータ」で説明しているとおり、字体違いによる検索漏れの可能性があり、それを避けるために利用してもらえる「新旧字体変換ツール」を作製した。詳細は「『聯珠詩格』全作品テキストデータ」の記述をご覧いただきたい。
これも、「『聯珠詩格』全作品テキストデータ」で述べているが、漢詩検索用ツールとして「漢詩データベース検索 CanD」を作製した。データベースへの作品の登録は進行中で、『聯珠詩格』は全作品登録が完了し、『三體詩』についてもいずれ全作品を登録する予定である。全作品の登録が完了すれば、『三體詩』についても、検索は「漢詩データベース検索 CanD」を利用してもらい、本テキストデータは閲読目的で利用してもらうのが良いと思う。
本文テキスト
さて、肝心の本文テキストだが、ひとつのページに一括掲載すると、編集作業時の動作が信じられないほど遅くなり、編集画面を開くだけで5分ほど待たなければならない状態になるため、以下の通り分割して掲載する。本文テキストは各ページで閲読していただきたい。